簡単に歯科衛生士学校に入ってからの流れを説明したいと思います。
歯科衛生士学校に入ってから何を勉強するか、またどんな実習をするのか
1年目
入学し、まず初めに新人研修ならぬオリエンテーションにて集団行動の確率それから座学で基礎を学びます。
・基礎分野
一般教養、社会福祉学、心理学、コミュニケーション論や歯科英語、自然科学の生物など
義務教育高校生で勉強したような内容もあり少し重複する部分があると思います。
・専門基礎分野
解剖学他、口腔解剖学・口腔衛生学、薬理学、歯科麻酔薬など
歯や口腔のことだけを勉強するわけではなく菌や体のつくり、薬など幅広く知識を習得します。
・専門分野
歯科衛生士概論、保存修復学、歯科補綴学、歯内療法学、歯科矯正学、口腔外科学、歯科材料学、レントゲン歯科放射線学、栄養指導学、高齢者歯科学。他には歯科衛生士として必ず必要な
3大科目の歯科予防処置論、歯科保健指導論、歯科診療補助論があります。
この3つには実習があります。実際に歯科医院や病棟にて臨床実習を行います。
そして、社会人としてのマナーやコミュニケーション能力も身につけます。
実際に現場で働く歯科衛生士は、子供から高齢の方まで年齢層は様々で色んな方と
臨機応変に対応する事を求められます。
2年目
座学で応用を学び臨床実習。
・歯科予防処置の実習
どのように歯周病や虫歯が進行していくか、どう予防していくのかという事を学び、その知識を元に
実習を行います。原因となる口腔内細菌取り除く方法としてクリーニングをしますがその行為が出来るのは
歯科衛生士だけです。正確には歯科医師と歯科衛生士です。その際先端の尖った器具を使用しますが、
安全に施術が出来るようにマネキンや相互実習で正しい使い方を学びます。また、虫歯の予防をする
薬剤塗布の実習、様々な練習を重ねて行きます。
・保健指導の実習
ブラッシング指導や生活指導の実習。定期的なクリーニングで口腔ない最近を除去することはもちろんですが、それだけでは予防する事が出来ません。日々のお家でのケアが重要になってきます。そこで正しい
ブラッシング方法を指導したり、おやつの与え方や生活習慣をどう改善すると予防につながるかを
実際に指導する実習を行います。
・外部実習(臨床実習)
歯科医院や病棟によって通っておられる患者さんの層も違えば働いている歯科衛生士も違うので、現場で学
べることは場所によって異なりますが、実際にどんな風に患者さんに接しているのか、どんな分野が
あるのか、たくさんの歯科衛生士を見て自分が将来どんな歯科衛生士になりたいのかを確立していきます。
実際に患者さんと触れ合ったり一般歯科だけではなく障害者歯科、矯正歯科、小児歯科、高齢者施設、
幼稚園、小学校など様々な現場で専門分野を学ぶ事ができます。
将来確実にどこの現場で自分が習得した経験や知識がどこに生きてくるかは分かりませんが臨床で
臨機応変な対応やハプニングに冷静に判断対応できる人財となる大事な時間となります。
3年目
前半は臨床実習が続き、後半になると卒業試験そして国家試験勉強
三年生になってもしばらく実習は続きます。
実習は登校日以外は毎日ほぼ1日続きます。実習に行くだけでなく、スタッフの一人として患者さんから
スタッフからも見られるため日々指導をして頂いたり注意されたり教えてもらった事は常にメモを取り実習のレポートに記録していきます。だいたい二人くらいの患者さんの症例を毎日記録し観察してその日あった
出来事についての反省やいろいろな観点から気づきを書いて最低でも裏表合わせて8枚は平均でも書いて
提出します。
私個人としては1年生座学や学校内での実習はそこまで難しい、辛いという事はありませんでしたが
臨床実習は生半可な気持ちで乗り越えられるような簡単なものではありませんでした。
精神的にも体力的にも消耗がすごく朝は基本的に5時か6時起きで臨床実習先の人たちに迷惑をかけない
ように一番に着き実習着に着替え邪魔にならないように配慮し5時に実習を終え帰宅した後レポートを書く。
のですが、これが1時間やそこらで終わるようなものではないので寝る時間は毎日0時をすぎ遅ければ3時
それから倒れるように寝てまた朝方に起きる、、という生活が1年半ほど続きます。
国家試験対策
試験対策に入りまずは卒業試験を合格しなければ卒業する事ができません。
内容としては、国家試験で出題される問題も含まれていますが一気に試験モードに雰囲気が変わります。
生徒同士でも少しピリピリした空気が教室の中を包みます。この試験対策の時期を乗り越えれば
歯科衛生士の合格率は99%。ほぼほぼ合格したも同然です。この時期にいかに集中して勉強するかで
結果は変わります。
まとめ
1年生 基礎の座学
2年生 臨床、専門の座学 臨床実習
3年生 臨床実習 国家試験対策
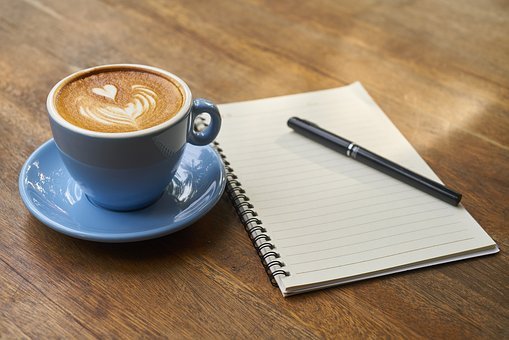


コメント